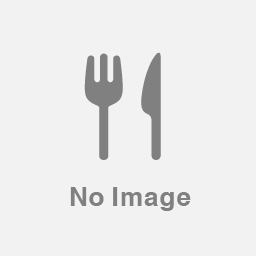「落下の解剖学」は第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で女性監督として史上3人目となるパルムドールを受賞、ゴールデングローブ賞最優秀脚本賞にも輝き、第96回アカデミー賞でも脚本賞を受賞した。
「落下の解剖学」
パルムドール賞はカンヌ国際映画祭における最高賞で、クオリティーの高さや、やや難解なストーリーや芸術的表現も評価の対象になると聞いていたので、前から気になっていました。
また、この謎めいたタイトル「落下の解剖学」にも引き寄せられ、先日劇場に観に行って来ました。

原題「Anatomy of Fall」
監督 ジュスティーヌ・トリエ / 脚本 ジュスティーヌ・トリエ / アンチュール・アラリ
キャスト ザンドラ・ヒュラー / スワン・アルロー / ミロ・マシャド・グラナー /アントワーヌ・レナルツ
公式の映画紹介には、フランスのサスペンス・法廷劇と書かれているようですが、私はこの映画は人間ドラマ、それも夫婦間・親子間の深層心理を描いた映画だと思います。
【あらすじ】
雪深い人里離れた山荘で、そこの住人が転落死する。発見したのは、視覚障害がある少年だけ。これは事故死か他殺か自殺か❓
ストーリーが進むうちに謎が深まり知りたくなかった事や見たくなかった事まであばかれて行くが、、、
分かりづらくて、最終的に観客の判断に委ねられるあたり、好き嫌いに分かれる内容ですが、私は好きでした。
【感想】
なんと言っても景色が綺麗。
フランスの山奥の、ポツンと建つ山荘はそれだけで絵になります。
冒頭から「ん、何だこれは」という違和感を感じるシーン。
イライラする大音量の音楽から、観ている者に「何か起こりそうな、絶対何か起こりそうな予感」をさせます。
この不自然な中、二人の女性は笑顔なんですが、それが却って不気味です。
ここまでは序章みたいな感じで、あまり意味がないように感じますが、実はこのシーンもすごく大事。
脚本賞を獲るだけあって、緻密に計算され尽くされている展開に、後から驚ろかされました。
次のカットは、視覚障害がある少年が犬の散歩から帰って、父の転落死を発見するシーン。

ここから話がワーッと一気に拡がっていきます。

「自殺」とも取れるし「他殺」とも取れる。
そして「他殺」だとしたら、疑われるのはその場にいた妻という事になります。
普通この線引きは事故現場の物的証拠とか参考人のアリバイとかが重要になって来ますが、それよりも、妻に殺意があったかどうかに焦点が絞られているのが、普通の事件物とは全く違う所です。
夫婦間の葛藤と家族の苦しみ
(ネタバレ含む)
フランス人の夫とドイツ人の妻、二人の間で使う言葉は中間をとって英語。
自国語で話さないで、お互い歩みよって生活しているかのようですが、実は仕事や家庭での役割で始終喧嘩が絶えない。
フランスに住んでいるのも、妻からしたら夫に合わせているという事で、住居についても不満です。
しかも作家として成功している妻に夫は嫉妬しているようで、彼は常にイライラしていたようです。
そして子供の目の病の原因は、下校時の時に遭った交通事故で、それは間接的に自分のせいだと悩む夫。
どこの家庭にも多かれ少なかれ、問題や悩みはあるものですが、それを口に出して言うか言わないかの違いも大きく関係してくるのでは❓と私は思います。
この家庭のいざこざ、口喧嘩を何と夫は、自分の作品のテーマの材料に使うつもりでずっと録音していたのです。
録音されていた事を妻は知らないので、つい酷い言葉で相手を罵ってしまっています。
これは法廷でとても不利になっていく。
でも妻は夫を愛していたと思うのですが、これは本人に聞かないと分かりません。
法廷での決め手となる子供の証言、これで判決が決まり一件落着のような終わり方をしますが、本当のところはどうなのか、観客に任せる形をとっているので、すっきりした終わり方ではありませんでした。
私は、夫は自殺だと思うし、息子も「そうであったと思いたい」ので、彼の心の目で両親を見ていた、その結果があの父親の自殺を仄めかす証言かなと。

最後の方に、息子が回想するシーンで、父親と二人で車で話す内容、実はあんな事は本当は父親は言っていなくて、あれはあの子供の妄想なのでは無いでしょうか。
この映画は「誰が」主体なのかで全く違う内容になってしまう恐ろしさを、かつての日本映画の傑作「羅生門」のように私達観客に教えてくれました。
最後に
人は見たいものしか見えないし、事実も時と共に自分の都合の良い方に解釈されていくような気がします。
またそれは、そうでも無ければ、現実が辛すぎてやってられないという事の裏返しなのかもしません。

軽井沢の家のデッキより
* Thank you as always *


にほんブログ村